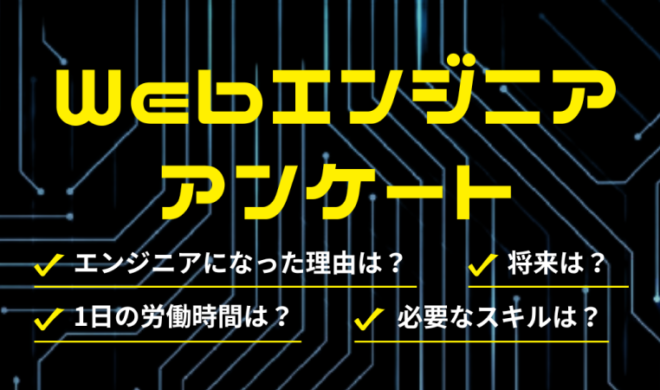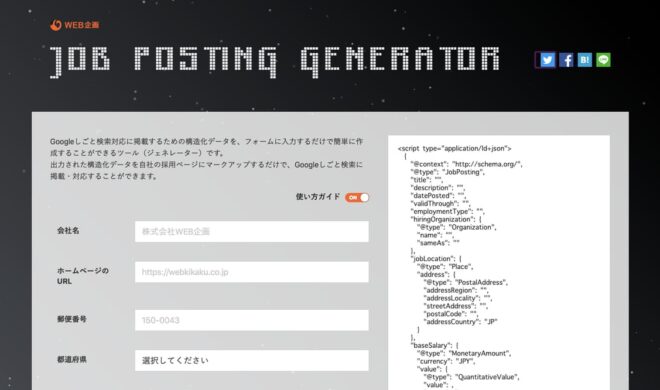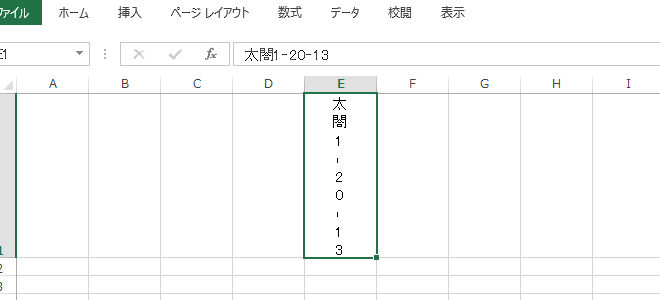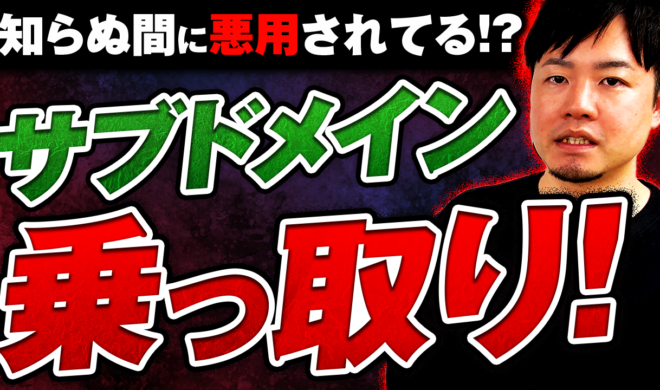【経営者必見】社内Webデザイナー採用の決断ポイント!内製vs外注どちらがいいの?
こんにちは、ウェブ企画パートナーズの竹内です。今回は、Webデザイナーを自社で雇用すべきかというテーマでお話しします。
私はウェブ企画パートナーズという会社を経営しており、経営者会などで「Webデザイナーを自社で雇用しようか迷っている」という相談をよく受けます。多くの場合、現在は外部の制作会社に任せていて、年間コストを考えると「これ、雇用する方が安いんじゃない?」と考えてのことだと思います。
今回は、考えるべきポイントをいくつかに分けてご紹介します。採用を考えている会社さんは、ぜひ最後までお付き合いください。
目次
スキルについて考える
Web領域の広さ
まず考えなければならないのがスキルです。Web領域は意外と広いんですよね。Webデザインをしただけではホームページには反映されません。デザインの後にコーディングといってWebサイトに反映させる作業があります。
さらに集客をしているなら、SEO(検索対策)・広告・Webマーケティング全般の知識なども必要とされることがあります。ホームページといっても、多岐にわたるスキルが求められるんですね。
どの領域までカバーできるかというのがまず一つのポイントです。
スキルの見極め難しさ
採用する際に、その会社さんはWeb制作会社ではないため、デザイナーの制作実績を見ても、Webデザインの能力があるかどうか判断するのは難しいです。デザインを見ても、どの人もオシャレそうなデザインに見えてしまうことがあります。
スキルがあるかどうかという問題と、それを見極められるかという問題があります。見極められないと、雇用して実際にデザインをしてもらった時に「あれ?実績と違った、変なものばかり出てくる」というリスクも考えられます。
実績の確認困難性
Webデザイナーの制作実績を確認するのは結構難しいことがあります。というのも、他社の過去の制作実績を「これを私がやりました」と言えないことがあるんです。例えば下請けや孫請けでやっていて、自分がやったと言うといろんなところに誤解が生じてしまう。秘密保持契約を結んでいる場合は、後から訴えられる可能性もあります。
かといって、仮想の企業を想像して「こういう制作物を作りました」というものは、自分本位で作られていて、クライアントからの指示なしの状態で作るので、結構いいものができあがりやすいんですね。どこかのイケてるサイトのデザインを模倣して作っていれば、いい感じになりますが、ゼロから一でやらせようとすると「アレ?」ということが起こり得ます。
適切な給与設定
デザイナーさんの適切な給与というのが分からないという問題もあります。相場を聞けば大体これくらいかなと思うのですが、当然雇用主としては人件費を抑えたいと思うものです。
一方で、腕の良い方を採用したいと思うはずです。そうなった時の適切な給与を提示できるかという問題もあります。
また、賞与をどうするのか、その方がどれくらい会社に貢献したのかを可視化できる体制が社内に整っているかなども考慮すべきです。
デザインスキルの継続性
デザインスキルには継続性という問題もあります。Webデザインのトレンドは移り変わっていくんですよね。アパレルの服のデザインや、iPhoneのアイコンなども時代によって変わっていきます。デザインは物理的には劣化しませんが、時代的には劣化するんです。
時流についていけるか、継続的にスキルアップして時代についていけるかという問題があります。外部の場合は、スキルアップしないと新規のお客様と契約できないので、どんどんスキルアップに努めるでしょう。しかし社内では、スキルアップに触れる機会はなかなかないことがあります。1社の案件しかやっていないので、スキルアップの機会が少ないんですよね。
デザインの得意領域
世の中のWebデザインには様々なデザインがあります。一軒家の内装を思い浮かべてもらうとわかると思いますが、ミニマリストのようなシンプルな部屋が得意な方もいれば、ロココ調のようなゴージャスなデザインが得意な方、女性雑誌のようなポップで可愛らしいデザインが得意な方、契約が取れるようなゴリゴリしたデザインが得意な方もいます。
例えば、女性向け商品のバナーを作ってもらったらすごくいい感じだったのに、男性向けのバナーを作ってもらうと「あれっ?これちょっと微妙だな」と思うようなデザインが出てくることもあります。
幅広いジャンルで高いクオリティのデザインを出してくれるデザイナーさんは本当に貴重です。業界に10年くらいいますが、かわいい系・かっこいい系から何から何まで高いレベルでこなしてくれるデザイナーさんは本当に貴重だと思います。
ただ、あらゆるデザインを高いレベルで出せるデザイナーさんも存在していて、その方がデザインが好きでスキルをどんどん高めていきたいと思っているなら、1社のデザインだけしていると自分のスキルアップの機会が減ってしまうという不安もあるでしょう。そのため、そういう方を採用しづらいという面もあります。
スピードについて考える
スキルの話は全体的にネガティブ寄りだったかもしれませんが、スピードに関しては確実に自社にデザイナーさんがいらっしゃった方がいいです。
普段からコミュニケーションを社内でとっているので、「こういうことをやりたいんだよね」という漠然とした要望を伝えても、社内の状況を把握しているため理解しやすい状況にあります。
「新商品のバナー、いつものアレみたいにやっといて」みたいな感じで言っても、密にコミュニケーションを取れていて関係性も良ければ、すぐに察して作業できます。専属でやっているので、スピード感を持ってバナーなどを作れるというメリットがあります。
コミュニケーションコストの低さ
スピードに加えて、コミュニケーションコストが安いというメリットもあります。外部の方に頼むと、正確に頼まないといい成果物が出てこないため、打ち合わせを重ねたりするコミュニケーションコストがかかります。社内に採用すると、そういった心配がないのはすごくいいポイントです。
リソースの柔軟性
制作会社に依頼すると、「今日たまたま納品日で立て込んでいるので難しい」ということはよくあります。これはあらゆる受注型ビジネスに発生することですが、リソースを完璧に空けておくのは難しいものです。
弊社も実際は社内にデザインできる者もいますが、基本的には外部パートナーと連携するスタイルです。大手ハウスメーカーのように下に工務店がくっついているパターンと思ってもらえばいいでしょう。それでもパートナーに「手空いてますか?」と確認してある程度スピード感を持って対応できるようにしていますが、それでも「今日どうしても難しい」ということはあります。
社内にデザイナーさんがいれば、優先順位を自社で決められるので、緊急の場合でもスピード感を持って対応できるというメリットがあります。
一貫したデザインテイスト
制作会社に外注すると、複数のデザイナーさんがいて、前回と同じデザイナーさんが担当してくれるとは限りません。「前回みたいな和風な雰囲気でやっておいて」と言っても、担当するデザイナーさんが違うと、テイストが変わってしまうことがあります。
そういう意味でも、自社の方がコミュニケーションコストの面で優位性があるポイントだと思います。
リスクについて考える
次に考えないといけないのはリスク、主に情報漏えいリスクです。
例えば、何かのビジネスでトップ争いをしている場合、ホームページのリニューアルやバナー作成一つとっても、なぜそういうことをしたいのかという自社の狙いを伝える必要があります。そうすると、自社のビジネスプランや今後の戦略を他社に漏らしてしまう可能性があるのです。
もし制作会社が1位と2位どちらもクライアントとしていた場合、もう1社が競合の情報を聞き出すというリスクも考えられます。そういう意味では、社内にデザイナーがいた方が情報漏洩は少ないでしょう。
実際、制作会社に「同業の実績はありますか?」と質問すると、同業の実績があるというのはクオリティの高さを示す一方で、情報漏えいのリスクもあることを意味します。
コストについて考える
最後に考えなければならないのがコストです。様々な面でのコストを考えた時に、それが見合うかどうかが重要です。
実際に採用してみたものの、デザインスキルが思ったよりなかった場合、その方を解雇するのは日本の法律では難しいので、金銭的な補償をつけて退職してもらうなどのコストが発生します。新しい方を採用する際の広告費や設備、教育コストもかかります。
デザインに問題がなくても、スピードが遅かったり、うまく意図が伝わらないといったコストもあるでしょう。辞めてしまった場合のコストなども含めて、全体を考えた時に見合うかどうかで判断するのがいいでしょう。
まとめ:Webデザイナーを自社に雇うべきか
結局、Webデザイナーさんを自社に雇うべきかという問いに対する私の考えは、2〜3名デザイナーさんを入れられるくらいの仕事量がある会社さんは、いよいよ本格的に採用を検討してもいいのではないかということです。
2〜3名いれば、先輩デザイナーに採用時のスキル見極めをしてもらえますし、優劣をつけて給与や賞与を出しやすくなります。スキルアップの面でも、デザイナーが複数名いれば互いに刺激し合って成長できますし、得意領域も分散できる可能性があります。
コミュニケーションコストなども互いに補完し合えるでしょう。リスクは防ぎようがないかもしれませんが、段階的に採用していくのがおすすめです。まず1名入れて外部パートナーと同時進行させながら、社内に慣れてきたらもう1名入れるといった形で、3名体制くらいになれば良い結果が期待できます。
一方、まだ1名分くらいしか仕事がない会社さんは、もう少し我慢して外部の制作会社に依頼した方がいいでしょう。スキルアップや継続性、スキルの担保がされますし、気に入らなければ依頼をやめて別の会社に頼むという選択肢もあり、リスクが低くなります。
デザイナー雇用のタイミング判断
| 会社の状況 | 判断 | 理由 |
|---|---|---|
| 2〜3名のデザイナーを入れられる仕事量がある | 雇用を検討 | スキルの補完、相互刺激によるスキルアップが期待できる |
| 段階的に採用できる体制がある | 雇用を検討 | まず1名から始め、徐々に増やしていける |
| 1名分程度の仕事量しかない | 外部委託を継続 | 固定費負担が大きく、リスクが高い |
| デザインの得意分野が偏っている | 外部委託を検討 | 幅広いデザインニーズに対応できる |
自社雇用 vs 外部委託の比較
| 観点 | 自社雇用 | 外部委託 |
|---|---|---|
| スピード | 迅速な対応が可能 | リソース状況により遅延の可能性あり |
| コミュニケーション | コストが低い、意図伝達が容易 | 打ち合わせや説明に時間がかかる |
| デザインの一貫性 | 担当者が同じで一貫性を保てる | 担当者が変わる可能性があり、テイストにばらつきが出ることも |
| 情報漏洩リスク | 低い | 競合他社に情報が漏れる可能性がある |
| スキルアップ | 機会が少なく、成長が遅れる可能性 | 多様な案件に触れる機会があり成長しやすい |
| コスト | 固定費になり、人件費や教育費などが発生 | 必要な時だけ費用が発生 |
| 柔軟性 | 限られた人材でカバー | 不満があれば依頼先を変更できる |
外部パートナーを活用する意義
この議論は、日本ではコンサル会社が割と嫌われているのと似ています。コンサル会社に対しては「中抜き」のイメージがあってあまり良くないかもしれませんが、実際には専門領域でスキルアップをずっと続けている会社という見方もできます。
工業製品を作る会社でも、良い製品を作るだけでは世の中に広まりません。それをうまく宣伝する力や営業力、マーケティング全般と掛け合わせて初めてビジネスが伸びるのです。
経営やマーケティングの領域でスキルアップを続けるのは、自社業界ばかり見ていると難しいものです。他業種の成功事例を自社業界に取り入れるなど、コンサル会社は常日頃からそういったスキルアップをしているので、外部から意見を聞く意味があるのです。
制作会社やWebデザイナーについても同じことが言えます。他社でうまくいった事例を「御社の業界でも試してみると良いかもしれません」と提案してもらえるのは大きなメリットです。
外部パートナーに頼るということは決して悪いことではないと個人的には思っています。こういった点も加味して、デザイナーさんを採用しようと考えている方は、総合的に判断いただけるといいでしょう。
以上、Webデザイナーを社内に雇用すべきかというテーマでお話しさせていただきました。皆様の疑問にお答えできていれば幸いです。