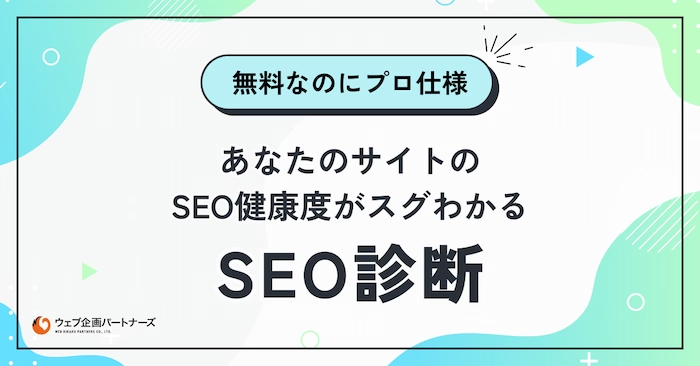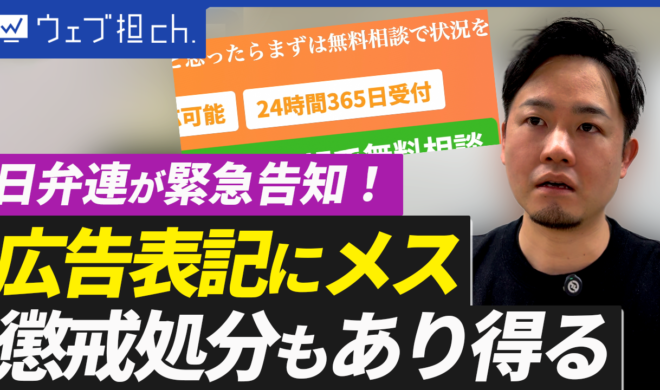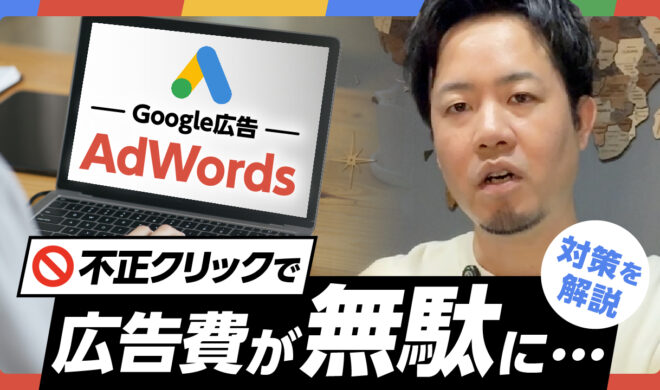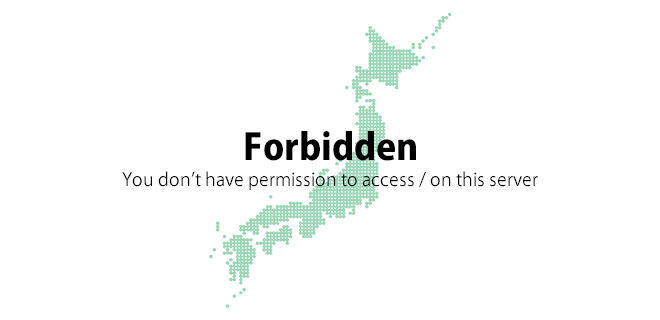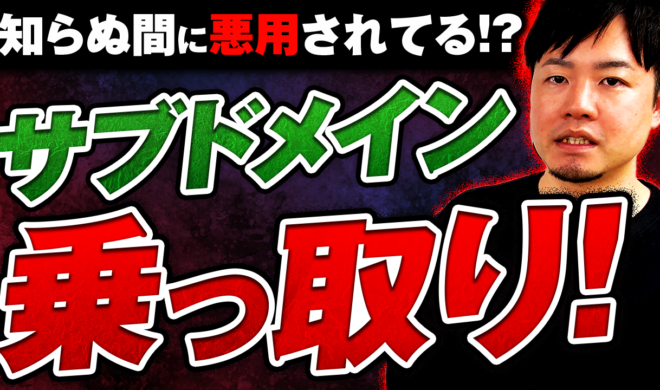【心理学的に解説】あなたのバナー広告が”完全無視”される本当の理由。「バナーブラインドネス効果」とは?
目次
なぜ、あなたのバナー広告は見られていないのか?
どうも、ウェブ企画パートナーズの竹内です。
今回は、「バナー広告がどうもうまくいかない…」という方向けに、その原因と対策についてお話ししていければと思います。
我々は心理学に詳しい制作会社でもありますので、広告がなぜ効かないのかを、今回は心理学的な視点から解説していきますね。
あなたは今日、バナー広告を何回見ましたか?
突然ですが、どうですかね。
今日、この記事を読むまでに、ウェブサイトやSNSなどで、いろいろなバナー広告が表示されたと思うんですけど、何回見たか覚えてますか?
「覚えていないよ」という方が、大半じゃないかなと思うんです。
それにはちゃんとした理由があるんですね。
無意識に広告を避ける「バナーブラインドネス効果」
実は、「バナーブラインドネス」という効果が心理学で確認されていまして、これこそが広告が無視される大きな原因の一つなんです。
このバナーブラインドネス効果というのは、実は結構古い研究でして、1998年、つまり20年以上も前にその効果が確認されたものなんです。
Web上での実験でそういう結果が出たわけですが、古いデータなので「今どうなんだ」というご意見もあるかもしれません。
ですが、皆さんもきっと、思い当たることがあるはずです。
Webサイトを見ているとき、いかにもバナーがありそうな位置だったり、広告っぽい雰囲気が出た瞬間に、すっと素通りしてしまうご経験はないですか?
あれがまさに、バナーブラインドネス効果なんです。
これが基本的には、広告の成果を妨げる障害となっています。
ですから、いかにこのバナーブラインドネス効果を遠ざけるか、この効果を超越したクリエイティブデザインを作れるかというところが、まず大事なポイントになります。
なぜ脳は広告を「見ない」ようにするのか?
この現象は、皆さんが意識的にやっているというよりは、無意識に脳が避けているということがデータで分かっています。
その理由は、いくつかあると考えられています。
原因1:免疫のような「慣れ」
1つ目は「慣れ」ですね。
だんだんと広告に慣れてくることによって、無意識に避けるようになってくる。まるで免疫のようなものを作って、「この辺は広告だな」と感覚的に分かったり、同じデザインの広告を前に見たことがあったら、無意識に飛ばしてしまったり。そういった慣れがまずあります。
原因2:目的以外の情報を遮断する「選択的注意」
2つ目は、脳のメカニズムに関わるもので、「選択的注意」というものがあります。
これは何かと言いますと、私たちは物事を何か見るとき、ほとんどの場合、何かしらの目的があって見ていますよね。
そのため、その目的に該当しない情報を無意識に見なくする処理を、脳が行っているということです。目的のもの以外は自動的にフィルタリングして見えなくしてしまう。これが選択的注意というものですね。
原因3:情報が多すぎる「情報の過負荷」
3つ目が「情報の過負荷」です。
人間の脳のキャパシティは限られていますから、あまりにたくさんの情報があると、それを避けようとしてしまうんですね。
どうですかね。例えば、ものすごく頭の良い方がいて、めちゃくちゃ早口で情報をまくし立ててくると、途中から「ちょっと聞く気になれないかも…」ってなると思うんですけど、あれは脳のキャパを超えて過負荷状態になり、情報を避けてしまうからなんです。
バナー広告も、その情報量の多さや、そもそも自社のバナー以外にも世の中にたくさんの情報が溢れているせいで、避けられてしまうことがあります。
大体この3つの要因によって、バナーブラインドネスという効果が発動される、というわけです。
この仕組みが分かっておくと、「じゃあ慣れさせないためにクリエイティブを変えた方がいいのかな?」「位置を変えた方がいいのかな?」「もうちょっと情報をシンプルに伝えた方がいいのかな」といった改善策が見えてくるということですね。
一方で、見せるほど好きになる「ザイオンス効果」
ここまでバナーブラインドネス効果が広告の敵ですよ、という話をしてきましたが、実は真逆の効果もあります。
それが「ザイオンス効果」です。
大体の方が知っていると思いますが、これは「単純接触効果」とも呼ばれるものでして、頻繁に会う人をちょっと好きになっちゃう、といった心理効果のことです。日本では「単純接触効果」という呼び方の方が、聞いたことがある方が多いんじゃないかなと思います。
この効果があるからこそ、広告の世界では「フリークエンシー」、つまり一人のユーザーに何回広告を表示するか、という考え方が重要になります。管理画面から「1人当たり大体3回くらい表示する」といった設定ができるんですね。
本来であれば、この単純接触効果を狙って、何回も広告を表示すれば好きになってくれるはずなんです。
やりすぎは禁物!見せすぎると嫌われる「摩耗効果」
しかし、話はそう単純ではありません。
単純接触効果でも、あまりにもたくさん見せられると、逆に「もう、ちょっと…」となってしまう効果があります。これを「摩耗(まもう)効果」と呼んだりします。
よく聞くのが、例えば子供の頃に毎日同じものを食べさせられて、それが嫌いになってしまう、という話があると思うんですが、あれに近いかもしれませんね。
3つの心理効果の複雑な関係性
つまり広告運用では、「そもそもバナーブラインドネスで見てもらえない」、「ザイオンス効果(単純接触効果)で好きになってもらう」、そして「見せすぎて摩耗効果で嫌われる」という、この3つの複雑な関係性を考えつつ、「じゃあ今はどれぐらいバナーを出すべきなのか」「もしくは、どういうデザインにするべきなのか」というのを、考えていく必要があるわけです。
「これが正解」と言えない時代の広告戦略
昔はWebを見るといったらパソコンだけを見ていれば良かったと思うんですけど、今はスマホが出てきたり、アプリで見せたり、バナーを見せるデバイスや場面が多様化しています。
そのため、時代時代でバナーの見せ方は変わってくるので、「これが絶対の正解だ」というのは、なかなか言いづらいのが現状です。
ただ、それは皆さん一人ひとりの状況が違うから言いづらいのであって、そのお客様一人ひとりに対しては、「今はこういう時期だから、ちょっとブラインドネスを考慮した改善が必要ですね」とか、「ザイオンス効果があるんで、バンバン打っていきましょう」とか、「摩耗効果をそろそろ感じると思うので、一旦止めてこの時期からもう1回やっていきましょう」とか。
そういうバランスを見ながら上手くバナーを出していかないと、効果はいかない、ということですね。
最後に:広告は「人の心」を動かすもの
基本的には、人間の心があって初めて行動が生まれるものです。
だからこそ、広告において心理学というのは非常に重要なんですね。
今回のバナー広告が上手くいかない理由で言うと、こうした心理学的な効果や研究が絡み合って、うまくいっていない可能性があります。
もし、これまでの話を聞いて、「そういえば、ちょっと最近広告を見せすぎてたな…」など、何か思い当たる節があった方は、ぜひ一度、改善をしていただく必要があるんじゃないかなと思います。