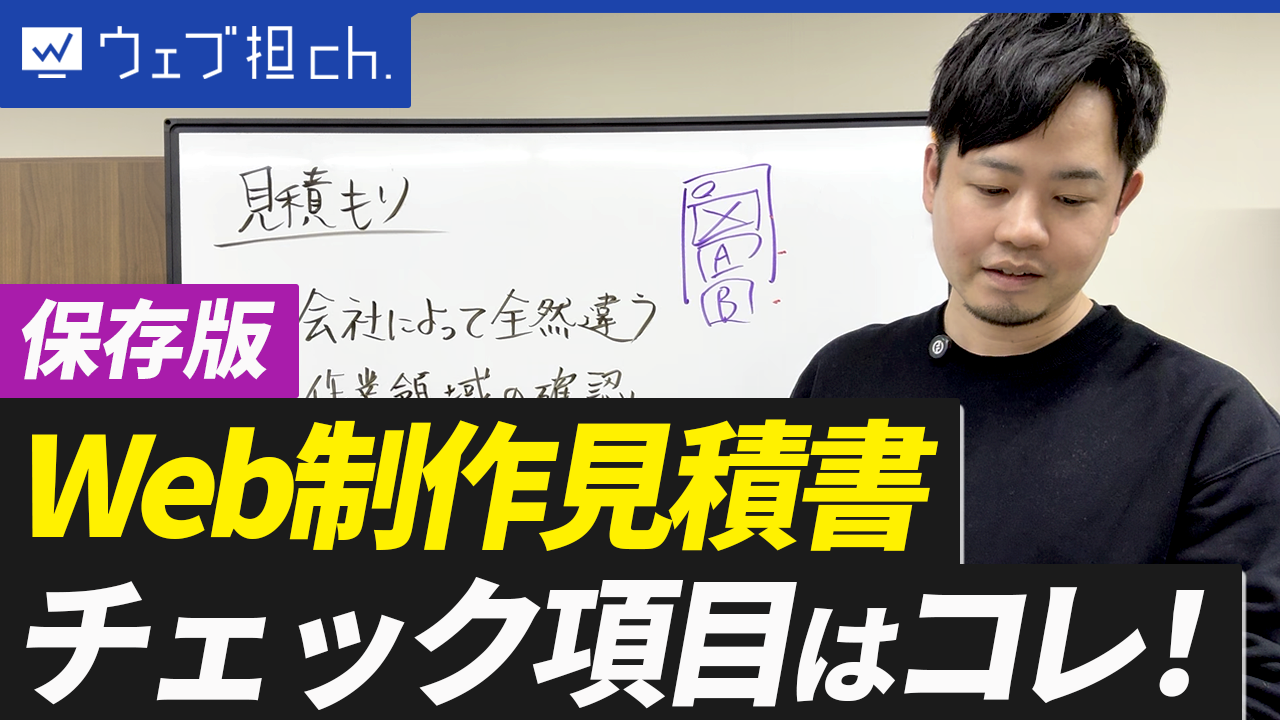
見積り依頼・確認
今回は、ホームページの見積もりについて解説したいと思います。
ホームページ制作の見積もり、まず知っておくべき大前提
まず、以前お話ししたRFP(提案依頼書)をちゃんと作っていただいて、同じ条件で各社に問い合わせをすると、見積もりや提案資料といった形で反響が来るかと思います。それらをどう比較すればいいか、というお話をさせていただいたんですが、今回は実際に出てきた見積もり、これの確認方法というか、注意事項をご紹介したいと思います。
会社によって見積もりの出し方は全然違う!
これを言ったら元も子もないかもしれませんが、まず一番にお伝えしたいのは、ホームページの見積もりは会社によって全然違うということです。 正直、ホームページほど会社によって見積もりの提出方法が違う業界はないんじゃないか、というくらい、本当にバラバラなんですよね。
依頼する側からしても、「どう見比べたらいいんだ?」というのは非常にわかりにくいと思います。なので、これはもう、頑張って解読していただくしかないんですが、いくつか代表的なポイントがあります。
見積書でよくある「違い」とは?
工程の記載、どこまで書いてある?
まず代表的なものとしては、工程の記載の仕方です。
例えば、企画費やプロジェクト管理費といったものがしっかり記載されている会社もあれば、制作物だけの値段が書かれていて、そういった管理費などをわざわざ記載しない会社もあります。
「1ページいくら」の考え方も色々
他にも、ホームページのページ数を「1ページ、2ページ」というようにカウントして費用を出す会社もあれば、私たちウェブ企画パートナーズのような会社ですと、例えばコンテンツ単位で見積もりを出すこともあります。
ちょっと具体的に説明しますね。例えば、あるホームページがあったとして、上部にロゴがあり、その下にメインの画像(メインビジュアル)が配置され、その下に「コンテンツA」、さらにその下に「コンテンツB」というように内容が続いているとします。
私たちの場合、この一つ一つのコンテンツブロックに対して値段をつけていくんですよ。なので、情報量が多くて縦に長いページであれば当然高くなりますし、逆に短いページであれば安くなる、という考え方です。
一方で、「1ページ」というまとめ方をしていると、どこまでの内容が含まれて同じ料金なのか、ぱっと見ではわかりづらいことがあります。もちろん、「1ページいくら」という方が、お客さんからしたら「10ページ作ったらこの金額ね」と、わかりやすい面もあるとは思います。
なんですが、「いやいやちょっと待てよ、このページはボリュームが少ないのに、なぜあのボリュームが多いページと同じ値段なんだ?」という疑問や、場合によってはクレームが起こる可能性も考えられますよね。
ですから、私たちはボリュームに応じて値段を変えることで、内容を減らせばその分料金も安くなるという、一見わかりにくいかもしれませんが、実は納得感のある料金体系にしているつもりです。
このように、見積もりの出し方や考え方は会社によって全然違うので、内容をよく精査して、総額でいくらかかってくるのかを見極める必要があるというのが、難しいポイントの一つです。
これは解決策を提示するというより、「そういうものなんだ」という前提を受け入れていただくだけで、少し見方が変わってくるんじゃないかと思い、ご紹介させていただきました。
見積もりチェック!「作業領域」はどこまで?
続いて、見積もりを確認する際にちょっと注意していただきたいというか、チェックしていただきたいのが、作業領域の確認になります。
誰が何をやるのか、しっかり確認しよう
どういうことかというと、例えば「会社概要ページを作ります」「代表挨拶もそのページに載せます」となった時に、その代表挨拶の文章は誰が書くのか、ということです。本来はその会社さんが書くべきだとは思うんですけど、「とりあえず書いてほしい」という状況だったとしますよね。
そうなった時に、文書の作成はどちらが行うのか、という問題が出てきます。
ホームページ制作って、業者に全部お任せでできるかというと、実際はそうじゃないんですよね。会社として発信したいメッセージがあるはずですし、もしメッセージがなければ、それを一緒に考えたり、作ったりしなければいけません。
料金表も、当然あるとは思いますが、それがまとまっていなかったり、口頭で「いくらだよ」って社内で伝わっているだけだったりしたら、それも改めて料金表として分かりやすいようにまとめて、業者に伝えなければいけません。
このように、ホームページを作る時には、発注側にも結構な作業が発生するんです。
その作業領域について、当然、制作会社は「資料をください」と言ってくるんですが、「いやいや、そこはやってよ」ということもあるわけです。なので、やってほしいことが、ちゃんとやってもらえる範囲に含まれているのかを確認した方がいいです。
初めてのホームページ制作で戸惑わないために
ただ、これが難しいのは、ホームページを作ったことがない方だと、どんな作業が発生するのか、なかなかわからないと思うんですよ。
ですので、今後、ホームページ制作でどのような作業が発生するのか、そして自分たちは何をしなければいけないのか、といったことを解説するコンテンツも予定していますので、そちらもご覧いただいて、なんとなく作業の全体像を掴んでから、「これを制作会社はやってくれるのかどうか」を確認していく、という流れが良いかもしれません。
代表的なものとしては、先ほど挙げた文章作成だったり、あとは現在ホームページがない場合だと、サーバーの構築やドメイン取得の代行までやってくれるのか、といったホームページ制作周りの作業もありますので、その作業領域をきちんと確認していただくのが大事になります。
要注意!「追加費用」が発生する可能性は?
続いては、先ほどの作業領域の話と少し似ているんですが、追加費用が発生するかどうかを確認するといいんじゃないかと個人的には思います。
要望と成果物の「ズレ」が追加費用を生むことも
これは制作会社によって結構スタンスが違うところがあるんですが、皆さん、ホームページ制作にあたって色々な要望を言いますよね。「例えばこういうことをやってみたい」「あんなことも実現したい」と。
それに対して、制作会社がどう応えるか、という話です。例えば、「会社の強みが見えるような図解を何か作って、それをホームページに載せてほしい」と依頼したとします。
制作会社はその図解を作るにあたっても、やり方が色々あるんですよ。例えば、AIツールを使って図解をパパっと作るようなやり方もあれば、デザイナーをしっかり入れて、分かりやすく、しかもサイトの雰囲気に合わせてリッチな図解を作るパターンもありますよね。
これって、同じ「図解を作ってほしい」という要望に対して、出てくる成果物の予想が、発注側と受注側ですり合わせがうまくいってない可能性があるんですよ。
それは制作会社も、ちょっとは分かっているはずなんです。なんですが、やはり安い方がお客さんを獲得しやすいので、安い方の作業内容で見積もりを作っている可能性があるんです。
そして、いざ蓋を開けてみて、出来上がったホームページを見てみたら、「いやいや、この図解、もっとちゃんとサイトの雰囲気に合わせて作ってよ!」ということが起こるかもしれないわけです。
「追加費用ありそう?」と正直に聞いてみよう
なので、そこをなんとか巧みに、「この見積もりで、弊社の要望は伝えたと思うんですが、もし追加の費用が発生する可能性があるとしたら、どういうところにありますか?」とか、「そもそも追加費用が発生する可能性はありそうでしょうか?」と、確認していただけるといいんじゃないかと思います。
そういう時に、「こういうところは確かに、ご要望の内容によっては追加の費用が発生する可能性がありますね」というふうに正直に言ってくれる会社もあると思います。そこを参考にするといいでしょう。
もし1社だけに見積もりを取っていた場合は、親切な業者は現れないかもしれませんが、何社か見積もりを取っていれば、「こういう部分は、確かにお客様のご要望の深さによって、追加費用が発生してくる可能性があるかもしれませんね」と、ちゃんと説明してくれる会社はあると思います。
逆に、何も言わない会社は、単純にその可能性を忘れていただけか、そこまで気が回らなかったか、あるいは、ちょっとせこいことをしようとしているか、どれかだと思いますので、「この見積もりで、追加費用が発生する可能性はありそうですか?」というのは、聞いてみていい質問の一つだと思います。
完成後も重要!「修正」にかかる費用は?
続いてが、修正の費用です。これは、ホームページが完成した後の話になります。
完成後の追加・修正費用が高額になるケースも
例えば、見積もりが100万円だったとして、それでホームページが完成しました、おめでとうございます、と。
作り終わった後で、「あれなんだけど、ちょっと1ページ増やしたいんだよね」というふふに伝えた時に、「なるほど、分かりました。スポットでの対応も承っております」ということで、その1ページの追加の費用が、例えば50万円くらいすると言われたら、「いやいや、ホームページ全体の半分の値段もするじゃないか!」となりますよね。
ただ、ホームページを作ってもらってしまっているので、なんとなくその業者に依頼せざるを得ないような雰囲気があるんですよね。なので、ちょっと高い費用でも払わなければいけない、ということも起こり得ます。
ベンダーロックインに注意!
また、「ベンダーロックイン」と言って、その業者しか触れないような特殊な仕組みでホームページが作られてしまった場合、修正費用が高くても、その業者に依頼するしかなくなってしまいます。また一から作り直すとなると、さらに大きなお金がかかってしまいますからね。
ですから、「仮にこういう修正をしたら、いくらになりますか?」というのは、契約前に聞いておくのが大事です。
なので、ホームページを運用していく中で、修正しそうな箇所をあらかじめ把握しておくのは重要です。
よくあるのは、採用情報系です。採用情報に従業員の写真が載っていて、その従業員が辞めてしまったので写真を差し替えなきゃいけない、といった時に追加の費用が発生してくる可能性がありますよね。
あとは、新しいサービスが追加された時に、サービスページを追加する可能性がありそうだな、とか。
このように、修正が発生しそうなことって、ある程度予想がつくじゃないですか。それに対して、「例えば、このくらいの修正だと、いくらぐらいですか?」というのは、聞いてみるのはアリかなと思います。
実際に、私たちウェブ企画パートナーズにお問い合わせいただいたお客様で、ある業者に依頼することがもうほぼ決まっていたけれど、「追加の修正の費用はだいたいどれくらいですか?」と質問してみたら、それが予想外に高くて、「これは新しい業者を探さなきゃ」と言って、私たちにご相談してくださった、というケースもありました。ですので、これは良い質問じゃないかなと思います。
見えない部分も大切!「内部SEO」はどこまでやってくれる?
これは最後のところで、ちょっとマニアックな話になるかもしれませんが、内部SEOについてです。
ホームページって、見栄えが良かったら、一般の人からすると「綺麗なホームページになったな」というのは分かると思うんですけど、内部SEOというのは非常に見えづらいので、これを何をやっていただけるのかは、セカンドオピニオン的に、誰か身の回りに詳しい方がいたら聞いていただきたいと思うくらい、専門的な部分です。
SEO対策、実はやることがいっぱいある!
これ、相当やることがあるんですよ。そして、相当やることがあるんですが、かつ、やらなくてもお客様から文句を言われないところでもあるんです。なぜなら、お客様には分からないからです。
なので、ここをどこまでやるのか、というのも実は見積もりの差に出てくるポイントだと思います。
例えば、どのような項目があるかと言いますと…(ここで具体的な項目を説明するために資料を見ている様子を、文章で説明しますね)
私たちウェブ企画パートナーズでは、細かいところまでSEO対策を希望されるお客様のために、オプションとして具体的な施策内容をリストアップしています。
OGP設定とは?
例えば、OGP設定ですね。これは、ホームページのリンクがLINEやFacebook、X(旧Twitter)などのSNSに貼られた時に、そのページのサムネイル画像やタイトル、説明文(ディスクリプション)がちゃんと適切な形で表示されるようにするための設定です。OGP設定をしていないと、意図しない画像が表示されたり、ページの魅力が伝わりにくくなったりします。
画像の拡張子も重要!
あと、画像の拡張子です。「jpeg(ジェイペグ)」とか「png(ピング)」とかは聞いたことがあると思うんですけど、最近は「WebP(ウェッピー)」とか「AVIF(アビフ)」といった、ファイルサイズが軽くて表示が速く、しかも画質が綺麗という新しい画像の拡張子も登場しているんですよね。それに対応させるのかどうか、という点です。
HTML/CSSの圧縮で表示速度アップ
あとは、HTMLとかCSSといったソースコードの圧縮ですね。ホームページを構成しているファイルを圧縮しておくと、サイトの読み込みが速くなります。本当にわずかな差かもしれませんが、そこまでしっかりやりたいかどうか、というところです。
構造化データで検索エンジンに情報を伝える
さらに、構造化データというものもあります。例えば、「この会社情報は〇〇です」というように、検索エンジンに対してページの内容をより具体的に伝えるためのデータです。会社情報だけでなく、よくある質問(FAQ)など、たくさんの種類の構造化データがあるので、それをきちんと対応させるかどうか、というのもあります。
セキュリティ関連の施策も
あとは、セキュリティ関連でも、例えば特定のページにアクセス制限をかけるためのBasic認証をきちんと設定できるか、などですね。
ちょっとピックアップしただけでも、みなさん多分あまり聞き慣れない言葉が多かったんじゃないかと思うんですが、そういった内部でやれること、クオリティを上げられることは実はたくさんあるんですよね。
「SEOに強い」のホントのところ
これ、なかなか伝わりにくいんですよ。だから、「SEOに強いです」と言っている会社が、具体的にどこまでやってくれているのかというのは、なかなか一般の方には伝わらないところがあって、「SEOに強い会社」と「そうでない会社」を見分けるのが難しい要因の一つではあると思います。
ですので、そういった内部の施策をどこまでやってくれるのか。
もし、「ビジュアルさえ良ければよくて、ホームページに誰もユーザーが来なくても大丈夫だよ」という方、例えばパンフレットや名刺から直接アクセスしてくれればそれで十分です、という方はそこまで気にしなくてもいいかもしれません。
でも、「ちょっとは検索に引っかかりたいな」という方だったら、SEOに強いと謳っている会社にも見積もりを取って、逆に、デザインが強いと言っている会社に「こういうSEOの内部施策ってやってくれるんですか?」と聞いてみると、もしかしたら「やりますよ」と言って、そこまでしっかり対応してくれるかもしれません。
内部SEO、つまり、SEOの内部施策やセキュリティ対策も含めて、ホームページの内部的な部分をどこまでやってくれるのか、確認していただく必要があると思います。
もしよろしければ、私たちウェブ企画パートナーズにもお問い合わせいただいて、「内部施策ってこういうことをやってくれるんだ」というのを、他社さんの見積もりと見比べていただいて、決定していただくのがいいと思います。
まとめ:ホームページ制作の見積もりで後悔しないために
前提:会社によって見積もりは本当に違う!
まず大前提として、会社によって見積もりの内容は全然違うんですよね。これは本当に、業界を代表して「申し訳ない」と言いたいくらいなんですが、ある意味しょうがない部分もあるんです。ホームページ制作の費用の大部分は人件費なので、それに対してどう料金を設定するのか、その見せ方や考え方も会社によって全然違ったりするんですよね。
確認すべきは「作業範囲」と「内部施策」
こういう前提がある以上、注意するところとしては、作業関連の確認、つまり、先ほどお話しした作業領域や、後から発生するかもしれない追加の費用、修正費用といったところ、そして、内部的にどこまでやってくれるのか、といった部分をきちんと確認していただけるといいんじゃないかと思います。
相見積もりで「なぜ違うのか」が見えてくる
あとは当然ですが、どの会社からも同じ条件で見積もりを出してもらわないと、費用の差がどこにあるのか分かりません。同じものを作ったはずなのに、なぜA社とB社で200万円も違うのか、といった疑問も、見積もりの詳細を見比べることで、「ああ、B社はこういうところまでしっかりやってくれるから、この価格なんだな」と分かるかもしれません。
ですので、いろんな会社に見積もりを取っていただく、いわゆる「相見積もり(あいみつ)を取る」というのは、ホームページ制作に限らず、何かを発注する際の前提として、やはり大事になると思います。ぜひ、あいみつを取っていただければと思います。
著作権など、契約に関する注意点はまた改めて
ちなみに、見積もりの話とは少しズレますが、著作権がどうなるとか、そういった契約に関するお話も重要です。それについては、また次のステップとして、「契約について」というテーマで詳しくお話ししようと思っていますので、そちらで説明したいと考えています。今回はあくまでも「見積書だけ」というテーマでお話しさせていただきました。
